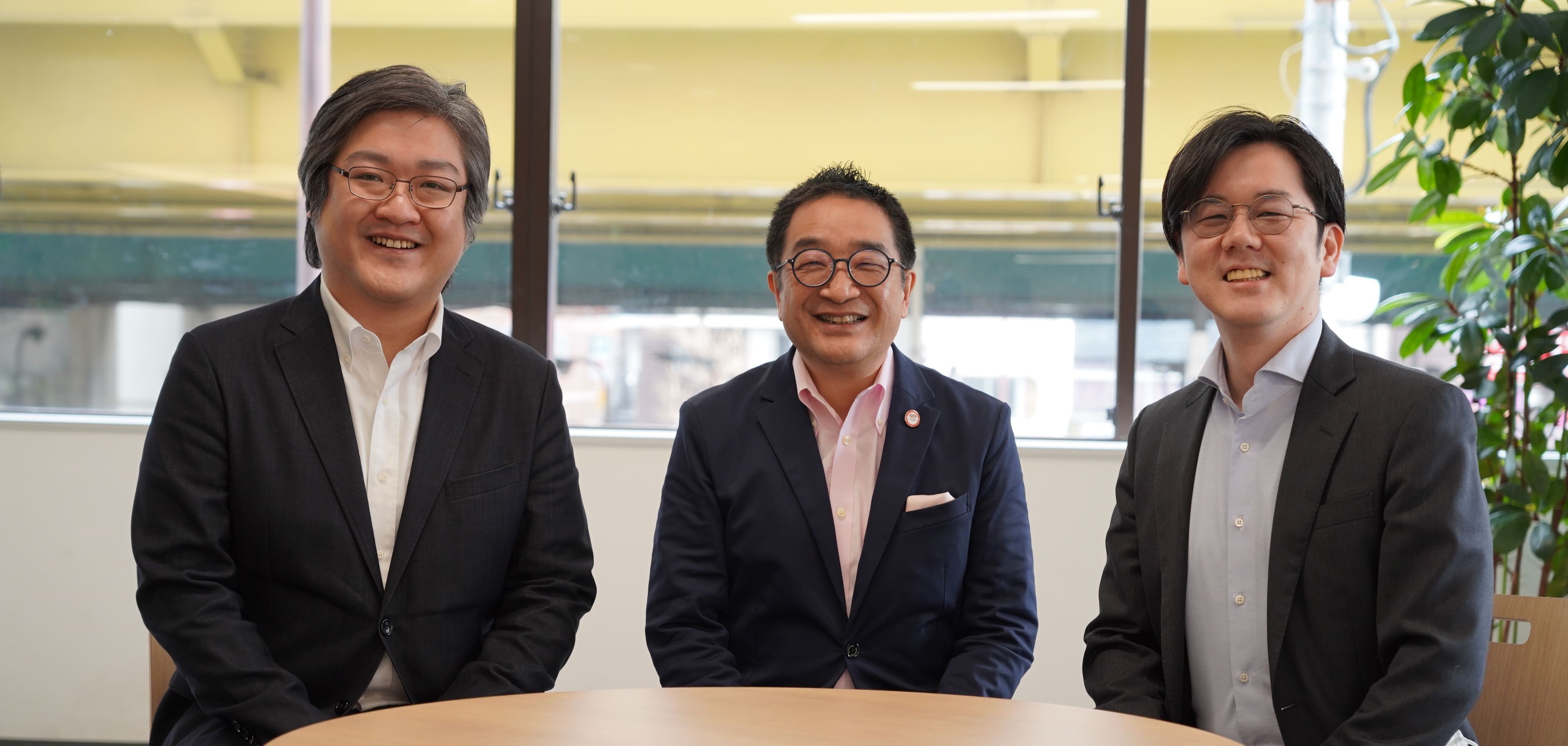コラムニストとして、そして大学教授、作家として活躍されるひきたよしあきさん。「言葉の力で、みんなが笑って暮らせる世界を目指す」をモットーに、コミュニケーションコンサルタントや講演者としてもひっぱりだこです。加えて最近では海外でも著作が出版され、その活躍は国境を越えてさらに広がっています。
そのひきたさんに、弊社は以前から設計事業部の設計プロジェクトでコンセプトメイキングやコピーの打ち出し方について、協力をいただいていました。現在はさらにその輪を広げ、弊社全事業部のブランディングコンサルタントをしていただいています。
そういった中、ひきたさんは弊社の教育事業部( 類塾 類学舎 自然学舎 )の在り方や理念に大いに共感され、「ひきたよしあき×類塾 特別講座」という共創イベントが今春に実現しました。この特別講座は開催前から予約キャンセル待ちが出るほど大評判となり、終了後も「次の開催はいつですか?」という声が続々と寄せられました(7月23日に第2回の特別講座を開催)。

今回のプロジェクトストーリーは、その特別講座の盛り上がりの中で生まれた「ひきたさんと弊社社員との鼎談(=ていだん、3人の座談会)」を紹介します。弊社社員として、齋藤仁巳・教育事業部次長/文系講師、山根教彦・経営統括部経営企画課長/人材課長、以下・役職略)が参加し、座談会は「よりよく生きる。活力持って生きるための学び」をテーマにして、特別講座と同じく大いに盛り上がりました。この座談会の内容はすでに類塾ホームページで記事として公開されています(全5話)。ここではその座談会記事の要約を紹介します。ぜひご覧いただいた後、類塾ホームページの全編をお読みいただければと思います。
1話 https://juku.rui.ne.jp/hikitayoshiakiruijuku_teidan1/
2話 https://juku.rui.ne.jp/hikitayoshiakiruijuku_teidan2/
3話 https://juku.rui.ne.jp/hikitayoshiakiruijuku_teidan3/
4話 https://juku.rui.ne.jp/hikitayoshiakiruijuku_teidan4/
5話 https://juku.rui.ne.jp/hikitayoshiakiruijuku_teidan5/
■第1話「入試の先にある言葉の使い方/体験のストックをして、そしてそれを考えた経験があるか」
国語を教える齋藤が「どうすれば読解力がつくかというのは永遠のテーマです」と話し、「自分の子どもに対して物語を理解する力や文章を読んで頭に入れる力がないんじゃないかと不安に思っている保護者は多い。子どもたちも自分も文字が嫌いだから読解力がないんじゃないかと思い込んでいるところがある」と言います。
言葉のプロフェッショナルであるひきたさんは「実は、読む力、書く力、言葉にする力は、“日常で体験のストックをして、それを考えた経験”からついていくものなんです」と話します。

類の教育事業部は4月から「自然学舎」という事業を立ち上げました。自社所有する大阪・彩都の山林で、江戸時代から続く棚田や自然に囲まれ、一回きりの体験ではない自然を通した学びができるプログラムです。
会談の中で、ひきたさんもこの「自然学舎」に大いに共感し、期待されています。実体験、特に自然と向き合った経験がその人の言葉と結びつく――。それが重要だということについて、ひきたさん、類塾とも同じ思いでした。
■第2話「親は自分の子の良い点を探す力が発揮できているか」
「発表するにも、本音を話すのにも、勇気がいる。だからまずは、発表してくれた“勇気”に対して、目一杯の拍手を送ることが大事」(ひきたさん)。この「発表したことへの敬意」は、ひきたさんが勤めていた広告代理店「博報堂」のフィロソフィーだそうです。ひきたさんは子どもたちの発表に対しても、この勇気を称え、親や周囲は拍手を送ろうと話します。そうすれば、子どもたちは自信を持って主体的になっていくのだと。

それを聞いた弊社の山根も「『自分は自信を持っていいんだ』ということを引き出すことは、すごく必要なことだと感じています。ひきたさんからよく、博報堂時代のエピソードとしてキャッチコピーを100個書いて持っていくとか、そのために本屋を何軒も回ったという話を聞くと、それくらいいろんなことに主体的にチャレンジすることで自信は生まれるのだと思います」と共感。
そして、自信が持てるのも、チャレンジすることができるのも、誰かからのエールやリスペクトがあるからだと、ひきたさんは言います。親は、子どもの良い点を探す力を発揮して、リスペクトを込めた拍手をいっぱい送りましょう。
■第3話「探求しよう」
類塾は早くから「探求」の学びを大切にしてきました。そして今、「探求講座」は類塾の学びの核となっています。その「探求講座」について、ひきたさんは「子どもたちが自由に話し出せる“良い仕組み”ができている」と評価してくれています。この第3話では、学校のグループワークとは少し違う、類の「探求講座」の魅力について語られています。

齋藤は「もともと類塾は『受験の先にある将来に生きる力』というテーマで50年間やらせていただいてきたのですが、時代の変化とともに2016年に『探求講座』という授業が始まりました。受験や教科を超えて、子どもたちが社会のこと、将来のことを探求していくことは言語能力の引き上げにもつながります」と述べています。
山根は類塾が探求を始めたことについて、こう言います。「社風として、なに? なぜ?と根本に立ち戻って考える精神が創業以来あって、それを教育の場でやってきたんだと思います」。
類塾の授業を見学したことのあるひきたさんは、授業で「探求しよう」というキーワードが出た瞬間、生徒たちが何か変わるような感じを受けたと話しています。そこから、子どもたちからどんどん発言が出てきたと。探求は「ちょっと博報堂のクリエイティブワークに近い」(ひきたさん)とし、探求が発言=言葉を生み出す力になっているのだと、ひきたさんは自らの経験を交えて語っています。
■第4話「言葉を駆使して生きる力/体と心と頭がつながった言葉/大谷翔平のどこが素晴らしいかということを僕たちは教えていかないといけない」
ひきたさんはいろいろな大学で学生たちを教えてきました。ある偏差値上位の大学の学生は、就活進路指導でエントリーシートに書く「座右の銘」について、ひきたさんにこう尋ねました。
「商社に行くには『一期一会』で大丈夫ですか?」
ひきたさんは驚いたそうです。一期一会はその学生の言葉ではなく、たとえば就職に合わせて言葉を選ぶこと、それは本当に言葉を駆使しているといえないと述べます。
一方で、別の大学生が書いたある座右の銘に、ひきたさんは感心したと話します。その大学生ならではの言葉だったからです。ひきたさんからその座右の銘とそれを書いた理由を聞いた齋藤、山根も同様に感心。果たして、その座右の銘、それを書いた学生の理由とは何なのでしょうか。これはぜひ本編で確認ください!
このように体と言葉が結びつかない時代、さらにネットで出回る、人を引き付けるための「強い言葉」を子どもたちは使うようになってきています。そうすると、感情の機微を表せなくなり、人生が行き詰まるようなことになると、ひきたさんは指摘します。
体と言葉がつながるようするために類塾では、第3話で書いた「探求」や、自然の中で体も心も頭もまるごと学びます。それは社会に出てからも生き抜く力になります。
齋藤は「将来の学び直しのためにも、子ども時代に豊かな経験をすることが大事。そこを見据えて、(類塾は)受験勉強と同時に、本来の学びの楽しさも伝えていきたいです」と言います。

ちなみに、ひきたさんは今、大リーグで大活躍する大谷翔平選手に注目しているそうです。その実力もすごいけど、大谷選手の「相手をリスペクトする言葉・優しい言葉・礼儀正しいところ」に社会は引き寄せられているのではないかと分析。現代では、ネットやSNSで強い言葉が使われており、気付かないうちに心がギスギスしてしまう、感情の機微が言葉にできなくなっています。そんな時代の中で、ひきたさんは「優しい言葉」が大切なのではないかと考えています。体と心と頭がつながった学びが大切なのです。
■第5話「みんなが笑って暮らせる国へ ~愉快に生きるために学ぶ~」
最後の回では、ひきたさんがかつてイタリアに行った際に知り合った現地の学校校長の言葉に感銘した話が語られます。
校長たちと「『何のために』学んでいるのか」という話に及び、校長は「愉快に生きるためだ」と話したそうです。ひきたさんは、「学びの本質はここに詰まっているのではないか」と言います。
ひきたさんによると、先のイタリアの先生はみんなに「愉快か?」「愉快か?」って聞きながら学校を運営しているそうです。
弊社の山根も「類塾も、『生き抜く力を育てる』と言うんですけど、その先も言葉にできたらいいなと思ってて。『愉快に暮らすため』って思うほうが幸せだなあ(笑)」と感じ入ります。
ひきたさんは「愉快もそうだけど、本源をどこに置くか、どこまで本源追求するかができてくると自分の芯ができる」と言い、「僕のスローガンは『みんなが笑って暮らせる国へ』で、人も自分も笑って、どう人を愉快にできるかというところが学びの本源だと考えています」と述べています。

ひきたさんの『みんなが笑って暮らせる国へ』というスローガンも、類塾の「活力ある社会を作りたい」という志も、思いは同じ。
「(我々は)活力ある子を作りたいし、社会人もみんなそういうふうにできたらいいなって、本源追求の軸は大事にしながら、未来に進んでいくということをやっていると思います」(山根)
愉快に生きるとは活力を持って生きるということと同じ。そして学びの本源は、愉快や活力を持って生きることにある――。3人の会談はこれに行き着き、幕を閉じました。
■最後に
今回の座談会(鼎談)は、学校に通う子どもさんをお持ちの親御さんはもちろん、大人にとっても大事な言葉や考え方がちりばめられています。要約で紹介しましたが、座談会の記事全文は類塾のホームページで公開されています。ぜひご覧になって「愉快に生きる。活力を持って生きる」ことの大事さ、そしてそれは言語能力と結びついていることを知ってほしいと思います。