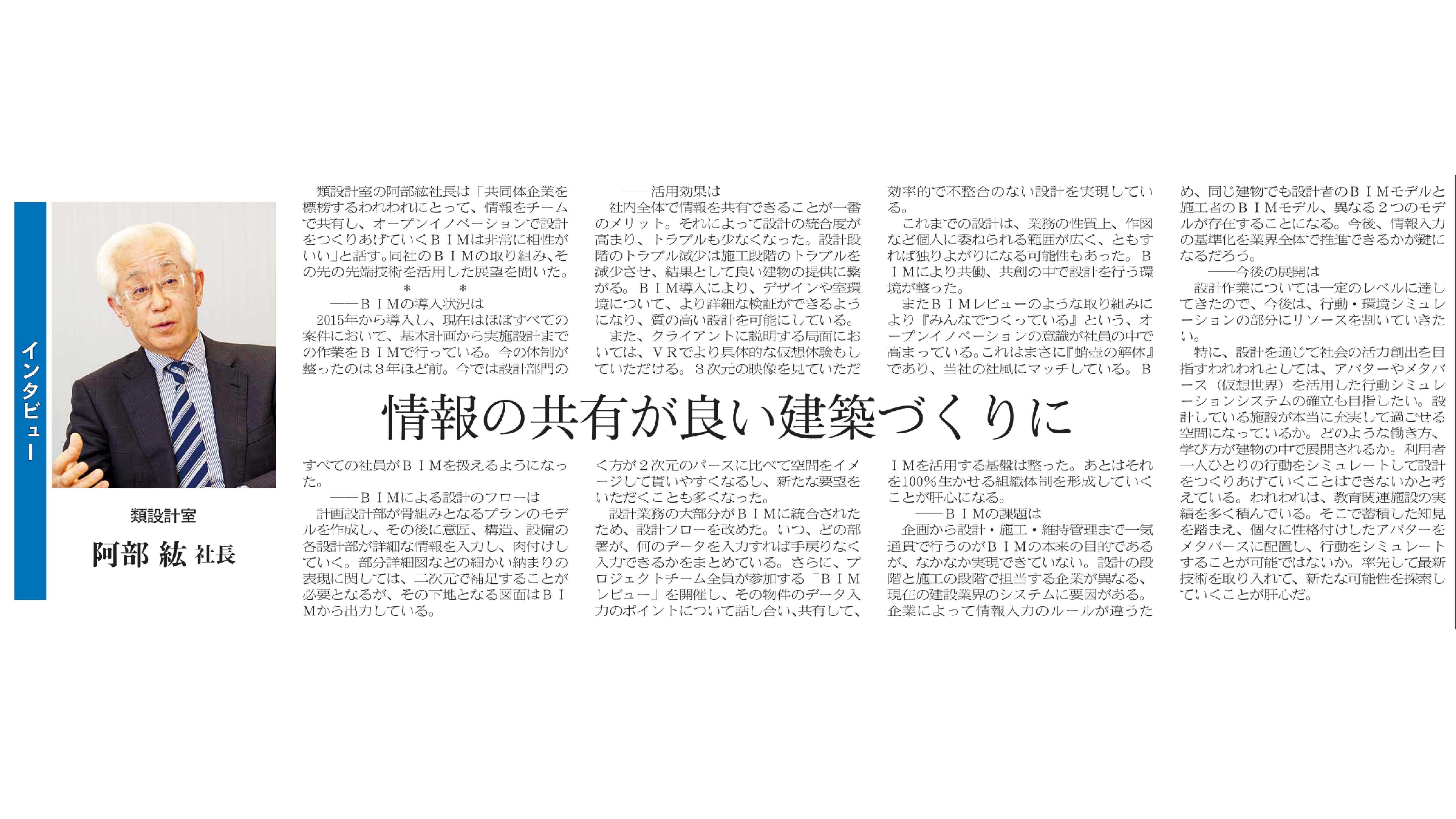「建設通信新聞:特集・踏み込む関西の建設ICT」に当社社長 阿部のインタビューが掲載されました

建設通信新聞(2022年11月14日)の「特集・踏み込む関西の建設ICT」に当社社長 阿部紘のインタビューが掲載されました。
建設現場の生産性向上を目的としていた建設生産システム改革は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の領域へと踏み込み、建設事業という視点から全体最適化を突き詰める動きに発展しています。建設通信新聞による今年のBIM特集は、建設ICT活用の最前線を紹介するものとして構成されています。
以下、記事全文
* * * * * * *
特集・踏み込む関西の建設ICT 類設計室/阿部 紘社長
【情報の共有が良い建築づくりに】
類設計室の阿部紘社長は「共同体企業を標榜するわれわれにとって、情報をチームで共有し、オープンイノベーションで設計をつくりあげていくBIMは非常に相性がいい」と話す。同社のBIMの取り組み、その先の先端技術を活用した展望を聞いた。
―BIMの導入状況は
2015年から導入し、現在はほぼすべての案件において、基本計画から実施設計までの作業をBIMで行っている。今の体制が整ったのは3年ほど前。今では設計部門のすべての社員がBIMを扱えるようになった。
―BIMによる設計のフローは
計画設計部が骨組みとなるプランのモデルを作成し、その後に意匠、構造、設備の各設計部が詳細な情報を入力し、肉付けしていく。部分詳細図などの細かい納まりの表現に関しては、二次元で補足することが必要となるが、その下地となる図面はBIMから出力している。
―活用効果は
社内全体で情報を共有できることが一番のメリット。それによって設計の統合度が高まり、トラブルも少なくなった。設計段階のトラブル減少は施工段階のトラブルを減少させ、結果として良い建物の提供に繋がる。BIM導入により、デザインや室環境について、より詳細な検証ができるようになり、質の高い設計を可能にしている。
また、クライアントに説明する局面においては、VRでより具体的な仮想体験もしていただける。3次元の映像を見ていただく方が2次元のパースに比べて空間をイメージして貰いやすくなるし、新たな要望をいただくことも多くなった。
設計業務の大部分がBIMに統合されたため、設計フローを改めた。いつ、どの部署が何のデータを入力すれば手戻りなく入力できるかをまとめている。さらに、プロジェクトチーム全員が参加する「BIMレビュー」を開催し、その物件のデータ入力のポイントについて話し合い、共有して、効率的で不都合のない設計を実現している。
これまでの設計は、業務の性質上、作図など個人に委ねられる範囲が広く、ともすれば独りよがりになる可能性もあった。BIMにより共働、共創の中で設計を行う環境が整った。
またBIMレビューのような取り組みにより『みんなでつくっている』という、オープンイノベーションの意識が社員の中で高まっている。これはまさに『蛸壺の解体』であり、当社の社風にマッチしている。BIMを活用する基盤は整った。あとはそれを100%生かせる組織体制を形成していくことが肝心になる。
―BIMの課題は
企画から設計・施工・維持管理まで一気通貫で行うのがBIMの本来の目的であるが、なかなか実現できていない。設計の段階と施工の段階で担当する企業が異なる、現在の建設業界のシステムに要因がある。企業によって情報入力のルールが違うため、同じ建物でも設計者のBIMモデルと施工者のBIMモデル、異なる2つのモデルが存在することになる。今後、情報入力の基準化を業界全体で推進できるかが鍵になるだろう。
―今後の展開は
設計作業については一定のレベルに達してきたので、今後は、行動・環境シミュレーションの部分にリソースを割いていきたい。
特に、設計を通じて社会の活力創出を目指すわれわれとしては、アバターやメタバース(仮想世界)を活用した行動シミュレーションシステムの確立も目指したい。設計している施設が本当に充実して過ごせる空間になっているか。どのような働き方、学び方が建物の中で展開されるか。利用者一人ひとりの行動をシミュレートして設計をつくりあげていくことはできないかと考えている。われわれは、教育関連施設の実績を多く積んでいる。そこで蓄積した知見を踏まえ、個々に性格付けしたアバターをメタバースに配置し、行動をシミュレートすることが可能ではないか。率先して最新技術を取り入れて、新たな可能性を探索していくことが肝心だ。