追手門学院中・高等学校
教頭
辻本 義広Yoshihiro Tujimoto
大阪府・茨木市にある追手門学院中・高等学校(以下、追手門中高)は、「独立自彊(どくりつじきょう)・社会有為」を掲げ、生徒主体の学校運営で人気を集める中高一貫校だ。校舎の設計を行うにあたって、類設計室は教育のあり方、授業のあり方を共に模索し、教育コンセプトづくりから携わった。足掛け6年のプロジェクトを終え、竣工から5年が経った今も、その交流は途絶えることなく、クライアントと設計事務所の関係性を超えた強固なパートナーシップが築かれている。追手門中高にとって類設計室が「イノベーションを起こしてくれるパートナー」となるまで。その軌跡を追った。

追手門学院大学がJR総持寺駅北エリアに茨木総持寺キャンパスを新たに開設するのに伴い、追手門中高の移転が決まったのは2015年頃のこと。新校舎を建てる上で、新たな学びを展開したいという追手門中高の強い意向を受け、教育コンセプトづくりから類設計室はプロジェクトに参画した。教育現場と設計事務所が一体となって、学びのあり方から議論する。本質をともに追求することで、目指す姿が少しずつ具現化していった。
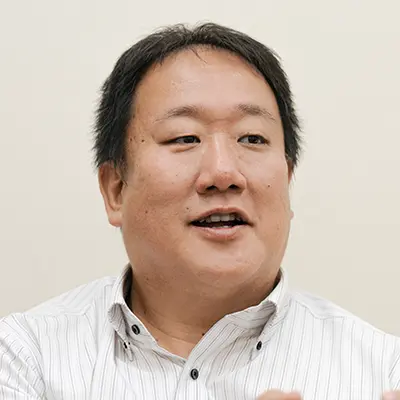 辻本:
新校舎で学んだ生徒たちが社会に巣立つ2030年の社会を想像するところから、一緒に考えていきましたね。教育コンセプトを考えるところから入っていただけたのは、類設計室さんや類塾さんと、私たちの目指す方向が同じだったから。学校は大きく分けて2つあると思っていて、一つは特効薬型でもう一つは漢方薬型。前者はプレッシャーやペナルティなどといった外発的な動機づけで成績を上げていく。分かりやすい成果が現れるからものすごく好まれるけれど、反面、副作用が大きいんです。私たちが目指すのは漢方薬型。幼少期、遊びが学びだったような時期が誰しもあると思うのですが、あれこそが学びの本来あるべき姿。内側から意欲が湧き上がってくるような学びを提供したいと私たちは考えていました。類設計室も同様ですよね。
辻本:
新校舎で学んだ生徒たちが社会に巣立つ2030年の社会を想像するところから、一緒に考えていきましたね。教育コンセプトを考えるところから入っていただけたのは、類設計室さんや類塾さんと、私たちの目指す方向が同じだったから。学校は大きく分けて2つあると思っていて、一つは特効薬型でもう一つは漢方薬型。前者はプレッシャーやペナルティなどといった外発的な動機づけで成績を上げていく。分かりやすい成果が現れるからものすごく好まれるけれど、反面、副作用が大きいんです。私たちが目指すのは漢方薬型。幼少期、遊びが学びだったような時期が誰しもあると思うのですが、あれこそが学びの本来あるべき姿。内側から意欲が湧き上がってくるような学びを提供したいと私たちは考えていました。類設計室も同様ですよね。
 馬場:
私たちが教育事業部で運営する類塾や類学舎にも成績第一という考えは一切ありません。教育とは子どもたちの心を育むものであり、どうすれば子どもたちが生き生きと学べるか、学校から飛び出して社会に出た時に活力が生まれるか。そこに思いを馳せているところは、追手門さんと我々の共通するところだと思います。
馬場:
私たちが教育事業部で運営する類塾や類学舎にも成績第一という考えは一切ありません。教育とは子どもたちの心を育むものであり、どうすれば子どもたちが生き生きと学べるか、学校から飛び出して社会に出た時に活力が生まれるか。そこに思いを馳せているところは、追手門さんと我々の共通するところだと思います。
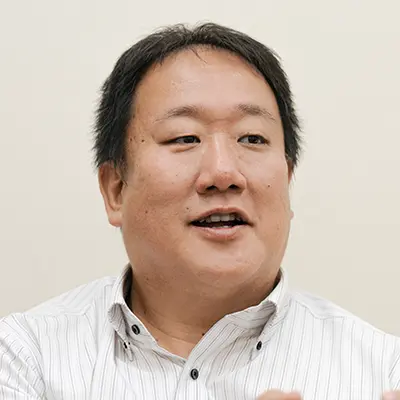 辻本:
どういう教育をしたいのか、どんな生徒を育みたいのか、その教育観から話し合って、教育の歴史や文献の調査、先端的な教育の事例調査や視察も一緒にしました。飲みながらつい熱くなって、青臭い話もたくさんしましたね。綺麗な学校とか、先進的な学校って言われるものはつくりたくない。「おもろいな、この学校」って言われるようにしたいんだと。「これ学校なん?」って聞かれるくらいのおもろい建物をつくりたいんだと。熱く語った夜のことは今でもよく覚えています。
辻本:
どういう教育をしたいのか、どんな生徒を育みたいのか、その教育観から話し合って、教育の歴史や文献の調査、先端的な教育の事例調査や視察も一緒にしました。飲みながらつい熱くなって、青臭い話もたくさんしましたね。綺麗な学校とか、先進的な学校って言われるものはつくりたくない。「おもろいな、この学校」って言われるようにしたいんだと。「これ学校なん?」って聞かれるくらいのおもろい建物をつくりたいんだと。熱く語った夜のことは今でもよく覚えています。
 喜田:
私もよく覚えています(笑)。クライアントと設計事務所という関係性を超えて、追手門さんとは、共につくってきたという感覚があります。ここまでが教育、ここからは建築というふうに線引きをしないで、学びも空間も本当に一体となって追求することができたと思います。
喜田:
私もよく覚えています(笑)。クライアントと設計事務所という関係性を超えて、追手門さんとは、共につくってきたという感覚があります。ここまでが教育、ここからは建築というふうに線引きをしないで、学びも空間も本当に一体となって追求することができたと思います。

基本構想に1年を費やしたのちに、類設計室が提案したのは、教室や廊下、図書館という枠組みを取り払い、校舎全体が学びの空間となる計画だった。「脱・教室」「脱・図書館」「脱・職員室」「脱・箱型校舎」、いずれも既存の学校施設の常識を覆すものばかり。ユニークな設計アイデアをかたちにすることができたのは、追手門中高と類設計室が、学びのあり方から共創してきたからに他ならないと、ディレクターの喜田は振り返る。
 喜田:
多様な学びの活動が校舎のどこでも行える「学習環境一体型の校舎」にしたいという想いが初めにありました。それと同時に現実的な課題としてコストの制約から面積をどう縮減するかというテーマがありました。廊下は通常、教室などの専用面積には含まれません。けれども廊下も含めて、校舎すべてを学びの場にすればいい。そんな逆転の発想から生まれたのが「脱・教室」「脱・廊下」といったアイデアです。一般的に、そんな提案を受けたら「廊下がなくて大丈夫?」「壁をそんなに動かして大丈夫?」と不安になることでしょう。誰も責任を取れないから、「やっぱり壁をつけてください」「いったんロッカー入れてください」と、従来の学校の姿になっていく。けれども追手門さんとは、生徒主体の学びを展開するために、個別・協働・プロジェクト型の授業の仕方とともに場の使い方を一緒に追求していたからこそ、「これがいい」と我々も確信を持って提案ができたし、追手門さんも受け入れてくれた。学びのあり方から追求していたからこそ、実現できた建物だと思います。
喜田:
多様な学びの活動が校舎のどこでも行える「学習環境一体型の校舎」にしたいという想いが初めにありました。それと同時に現実的な課題としてコストの制約から面積をどう縮減するかというテーマがありました。廊下は通常、教室などの専用面積には含まれません。けれども廊下も含めて、校舎すべてを学びの場にすればいい。そんな逆転の発想から生まれたのが「脱・教室」「脱・廊下」といったアイデアです。一般的に、そんな提案を受けたら「廊下がなくて大丈夫?」「壁をそんなに動かして大丈夫?」と不安になることでしょう。誰も責任を取れないから、「やっぱり壁をつけてください」「いったんロッカー入れてください」と、従来の学校の姿になっていく。けれども追手門さんとは、生徒主体の学びを展開するために、個別・協働・プロジェクト型の授業の仕方とともに場の使い方を一緒に追求していたからこそ、「これがいい」と我々も確信を持って提案ができたし、追手門さんも受け入れてくれた。学びのあり方から追求していたからこそ、実現できた建物だと思います。
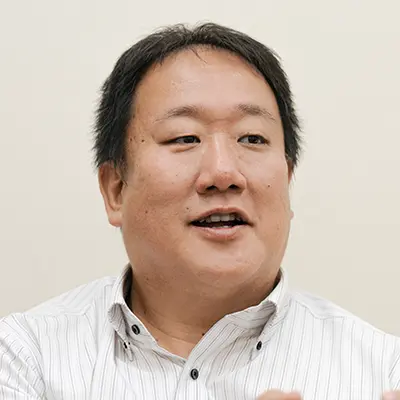 辻本:
教室とは、子どもを囲い込む場でもないし、教師の話を一方的に聞く場でもない。生徒は生徒の中で育つというのが、私たちの考え方。だからこそ、人の流れがつくれるように流動的なつくりにしてもらいました。何もない教室が、私は特に気に入っています。電子黒板のような最新鋭の設備は何もない。何もないからこそ、自分たちで好きなようにアレンジができるんです。教員の立ち位置ですら、決まりはありません。生徒の前に立たず、生徒の真ん中に教員がいたっていい。実際に、先生が一方的に「教える教室」から、生徒が主体的に「学ぶスペース」へと学びの場が変わってきています。
辻本:
教室とは、子どもを囲い込む場でもないし、教師の話を一方的に聞く場でもない。生徒は生徒の中で育つというのが、私たちの考え方。だからこそ、人の流れがつくれるように流動的なつくりにしてもらいました。何もない教室が、私は特に気に入っています。電子黒板のような最新鋭の設備は何もない。何もないからこそ、自分たちで好きなようにアレンジができるんです。教員の立ち位置ですら、決まりはありません。生徒の前に立たず、生徒の真ん中に教員がいたっていい。実際に、先生が一方的に「教える教室」から、生徒が主体的に「学ぶスペース」へと学びの場が変わってきています。
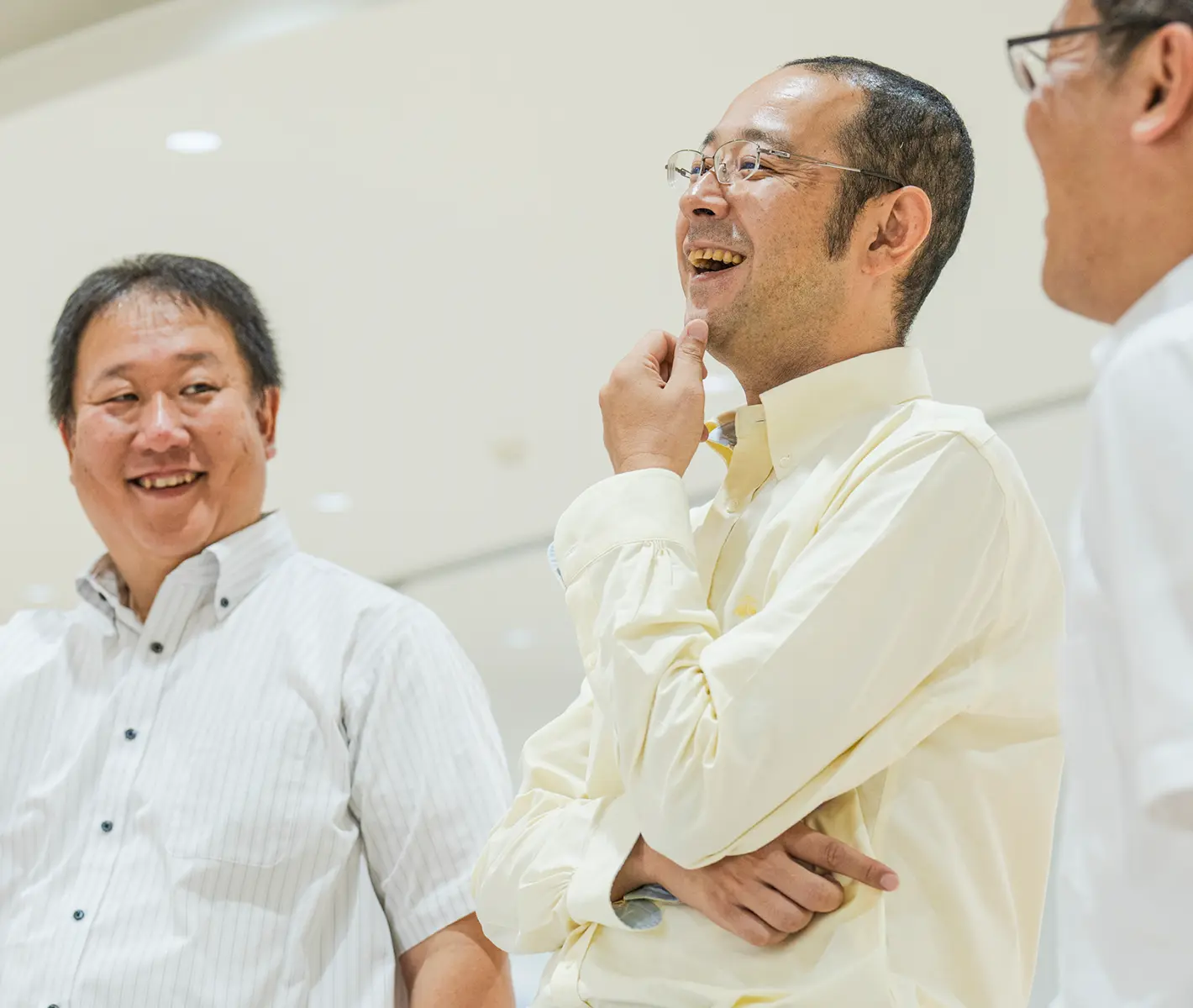

授業中も休み時間同様に生徒たちの元気な声がこだまし、静まり返った教室がひとつもない。教室で廊下で、開かれた図書室で、校舎のあらゆるところで、生徒たちが生き生きと活動している。竣工から5年が経過した今、追手門中高の校舎内には、類設計室が思い描いていた以上に活力のあふれる空間が生まれている。校舎が変わったことで、教員や生徒たちにも大きな変化があったと辻本先生は語る。
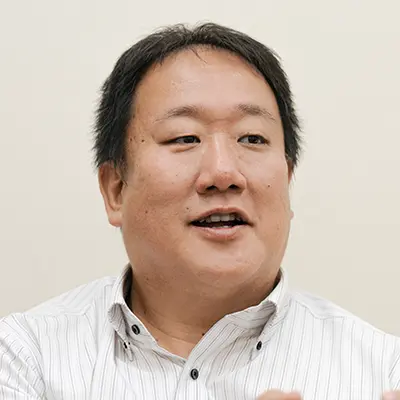 辻本:
教員の採用試験をしても、この場所で教育がしたいと受けにきてくれる人が増えましたね。建物の影響は非常に大きいと思います。生徒たちも以前の校舎に比べて元気で明るくなったし、本当に楽しそうに授業を受けてくれている。直接的ではないにせよ、建築が教育を変えるところは大いにあると思います。
辻本:
教員の採用試験をしても、この場所で教育がしたいと受けにきてくれる人が増えましたね。建物の影響は非常に大きいと思います。生徒たちも以前の校舎に比べて元気で明るくなったし、本当に楽しそうに授業を受けてくれている。直接的ではないにせよ、建築が教育を変えるところは大いにあると思います。
 喜田:
保健室に駆け込む生徒さんが明らかに減ったというお話も聞いています。一人で過ごせる居場所が少ないかもしれないと当初は懸念していたのですが、開放的な空間だからこそ、自分の居場所が教室だけに限られない。何かあっても隣の学年や先生との距離が近い。開かれた環境の方が、生徒たちの世界も広がっていくのだと思います。嬉しい悲鳴としては、生徒数が想定していた以上に増えて、教室が足りなくなってしまったところでしょうか。
喜田:
保健室に駆け込む生徒さんが明らかに減ったというお話も聞いています。一人で過ごせる居場所が少ないかもしれないと当初は懸念していたのですが、開放的な空間だからこそ、自分の居場所が教室だけに限られない。何かあっても隣の学年や先生との距離が近い。開かれた環境の方が、生徒たちの世界も広がっていくのだと思います。嬉しい悲鳴としては、生徒数が想定していた以上に増えて、教室が足りなくなってしまったところでしょうか。
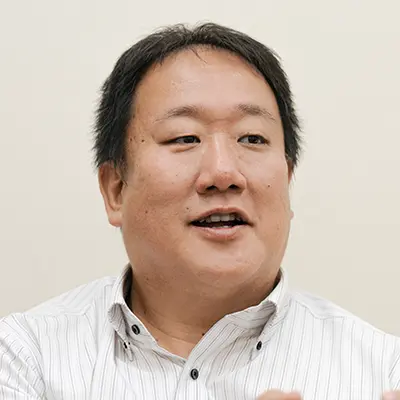 辻本:
おかげさまで生徒数は増えていますね。そのほかに感じる変化としては、進路を決めるときの生徒たちの思考。以前は大学名から進路が決まっていたんです。自分たちはSSクラスだから、上位の大学を目指すとか、自分は理系だからこの大学とか。今では第一希望に対するこだわりが、ものすごく強くなっています。これを学びたいから、この学校に行きたいとか、日本の受験システムが合わないから海外の大学に行きますとか。現役の高校生で、クラウドファンディングで起業している子もいます。探求的な学びや共同的な学びを通して、一人ひとりの子どもたちに没頭できるものが生まれている。これは本当に嬉しい変化です。
辻本:
おかげさまで生徒数は増えていますね。そのほかに感じる変化としては、進路を決めるときの生徒たちの思考。以前は大学名から進路が決まっていたんです。自分たちはSSクラスだから、上位の大学を目指すとか、自分は理系だからこの大学とか。今では第一希望に対するこだわりが、ものすごく強くなっています。これを学びたいから、この学校に行きたいとか、日本の受験システムが合わないから海外の大学に行きますとか。現役の高校生で、クラウドファンディングで起業している子もいます。探求的な学びや共同的な学びを通して、一人ひとりの子どもたちに没頭できるものが生まれている。これは本当に嬉しい変化です。

設計事業部だけでなく、教育事業部においても追手門中高と類設計室の共創がはじまっている。2024年には、類設計室の教育事業部の企画・運営のもと、山の中で自然体験を行う「サイエンスキャンプ」を実施した。中学1年生と2年生の180名を対象とした3日間のプログラムは、教育事業部がこれまで自然体験・仕事体験プログラム「自然学舎」で培ってきたノウハウが凝縮されている。
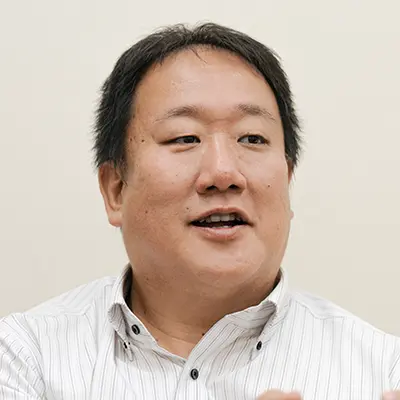 辻本:
はじめに類設計室から提案をいただいた時は、ぶっとんでるなと思いました(笑)。「なんで塾さんがここまですんのやろ」というのが最初の感想。正直、おもろいなと思いました。おもろい教育をしたいというのが前提としてありますし、ワクワク感を中心におきたい。子どもたちにいろんな体験をさせたいですし、本物に触れられる機会をつくりたいという思いはありました。
辻本:
はじめに類設計室から提案をいただいた時は、ぶっとんでるなと思いました(笑)。「なんで塾さんがここまですんのやろ」というのが最初の感想。正直、おもろいなと思いました。おもろい教育をしたいというのが前提としてありますし、ワクワク感を中心におきたい。子どもたちにいろんな体験をさせたいですし、本物に触れられる機会をつくりたいという思いはありました。
 馬場:
我々としても中高生向けのプログラムを構築していく上で、学校側のご意見をお聞かせいただきたいと思って、真っ先に追手門さんにご相談させてもらったのがきっかけです。「自然学舎」でこれまでも自然体験のプログラムはいくつも実施してきたのですが、土日がメイン。平日も自社所有の山や自社農場を学びの場として使っていただくために、学校と共創をしたいという思いは以前からありました。今回私たちが追手門さんに提案した企画は、自然体験を通して「全員がつくり手になる」というもの。プログラムを通して、失敗してもいいからどんどん挑戦しよう、というメッセージを込めていました。
馬場:
我々としても中高生向けのプログラムを構築していく上で、学校側のご意見をお聞かせいただきたいと思って、真っ先に追手門さんにご相談させてもらったのがきっかけです。「自然学舎」でこれまでも自然体験のプログラムはいくつも実施してきたのですが、土日がメイン。平日も自社所有の山や自社農場を学びの場として使っていただくために、学校と共創をしたいという思いは以前からありました。今回私たちが追手門さんに提案した企画は、自然体験を通して「全員がつくり手になる」というもの。プログラムを通して、失敗してもいいからどんどん挑戦しよう、というメッセージを込めていました。
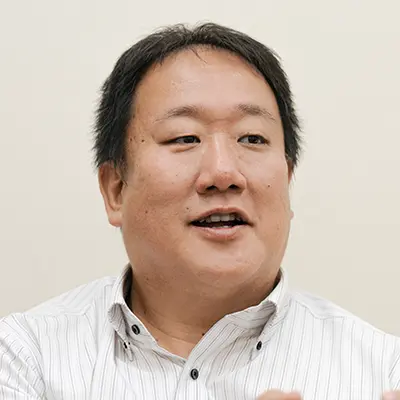 辻本:
当日は私も引率しましたが、やはり本当に面白かった。自然相手ですから、予定調和じゃないことが起こるんです。手順もやり方も全部決まっているプログラムじゃなくて、ちゃんと失敗するようにつくられているプログラム。最終日に子どもたちが発表する姿も見ていたのですが、ふだんはなかなか自分から喋らない子が発言している様子も見ることができたのも印象的でした。私自身にとっても学びの多い3日間になりました。
辻本:
当日は私も引率しましたが、やはり本当に面白かった。自然相手ですから、予定調和じゃないことが起こるんです。手順もやり方も全部決まっているプログラムじゃなくて、ちゃんと失敗するようにつくられているプログラム。最終日に子どもたちが発表する姿も見ていたのですが、ふだんはなかなか自分から喋らない子が発言している様子も見ることができたのも印象的でした。私自身にとっても学びの多い3日間になりました。

クライアントと設計事務所の関係を超えて、さらには設計から教育へと事業部をまたいで、追手門中高と類設計室の共創は続いている。最後に、追手門中高にとって類設計室がどのような存在なのか、辻本先生にお聞きした。
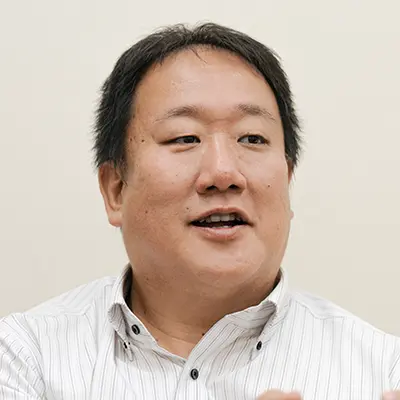 辻本:
教育のビジョンであったり、目標とするところが類設計室と我々は共通している。教育観の合意形成がしっかり取れているパートナーであるということが、まず前提にあります。類塾さんに対しては、塾とか学校とか、全日制とか定時制とか関係なく、類塾という場所がいろんな学びが提供できるプラットフォームになってほしいなと思っています。
辻本:
教育のビジョンであったり、目標とするところが類設計室と我々は共通している。教育観の合意形成がしっかり取れているパートナーであるということが、まず前提にあります。類塾さんに対しては、塾とか学校とか、全日制とか定時制とか関係なく、類塾という場所がいろんな学びが提供できるプラットフォームになってほしいなと思っています。
今、周りを見渡してみても、漢方薬型の学校は非常に少ないのが現状です。もちろん社会に出たら成果主義だし競争主義です。だからこそ、私は中高生の間は成果主義よりプロセス重視、競争主義より協働重視でありたいと思います。社会に適応する子をつくっていくんじゃない。自分たちで社会をつくっていく子を、私たちは育てていきたいのです。
子どもたちが多感な時期を過ごす場所なのだから、子どもたちの考えや志向にあわせていろいろな選択肢、いろいろな学び舎があっていいと私は思っています。環境が教育に与える影響は非常に大きいので、類設計室にはぜひ、環境から教育を変えていってほしいと思います。私たちにとって、類設計室はイノベーションを起こしてくれるパートナー。追手門はおもろい学校を目指していますが、類設計室も相当おもろい会社、おもろい塾やと思っています。
※本記事の内容は、2024年11月現在の内容になります。