東京設計室
計画設計部
桑島 直樹Naoki Kuwashima
2024年入社
新しい環境を求めて転職してきた社員たち。前職の経験を活かして、どんな活躍ができるのか、どんなキャリアを描けるのか、他社を経験したからこそ語れる類設計室の魅力をお聞きしました。

はじめに、皆さんの転職のきっかけを教えてください。
 菊地:
前職ではアトリエ系の設計事務所で、個人クライアントの住宅設計を行っていました。住宅は設計からできあがるまでのサイクルも早く、建築を学ぶ上では良い経験ができました。その上で、もっと技術力を高めながら、領域を広げていくことに挑戦したいと思ったのがきっかけです。転職先を探していたときに、いろんな会社のHPを拝見しましたが、類設計室は建築のデザインだけではなく、そのプロジェクトの背景やどんな使われ方をするのかといった建てた後の展望まで考え抜かれているなと感じました。人と人のつながり、社会とのつながりをつくっている印象を受けて、その姿勢に惹かれました。
菊地:
前職ではアトリエ系の設計事務所で、個人クライアントの住宅設計を行っていました。住宅は設計からできあがるまでのサイクルも早く、建築を学ぶ上では良い経験ができました。その上で、もっと技術力を高めながら、領域を広げていくことに挑戦したいと思ったのがきっかけです。転職先を探していたときに、いろんな会社のHPを拝見しましたが、類設計室は建築のデザインだけではなく、そのプロジェクトの背景やどんな使われ方をするのかといった建てた後の展望まで考え抜かれているなと感じました。人と人のつながり、社会とのつながりをつくっている印象を受けて、その姿勢に惹かれました。
 桑島:
私も前職はアトリエ系の設計事務所でした。きっかけとなった理由は二つあります。一つはいろんなビルディングタイプに挑戦したかったこと。前職では携わっていた物件の用途が限られていて、商業施設が中心。類設計室なら教育施設、研究・生産施設、文化施設を中心に様々なビルディングタイプに挑戦できると思いました。もう一つは、働く環境です。設計の仕事だからある程度の働き方は覚悟していたけど、残業も多かったし休みも少なかった。忙しくても一人で抱え込むことが多くて。将来を見据えたときに、類設計室の垣根のないオープンな風土や育成に配慮されたプロジェクト体制、丁寧なキャリア形成支援がある環境で働きたいと思ったんです。
桑島:
私も前職はアトリエ系の設計事務所でした。きっかけとなった理由は二つあります。一つはいろんなビルディングタイプに挑戦したかったこと。前職では携わっていた物件の用途が限られていて、商業施設が中心。類設計室なら教育施設、研究・生産施設、文化施設を中心に様々なビルディングタイプに挑戦できると思いました。もう一つは、働く環境です。設計の仕事だからある程度の働き方は覚悟していたけど、残業も多かったし休みも少なかった。忙しくても一人で抱え込むことが多くて。将来を見据えたときに、類設計室の垣根のないオープンな風土や育成に配慮されたプロジェクト体制、丁寧なキャリア形成支援がある環境で働きたいと思ったんです。
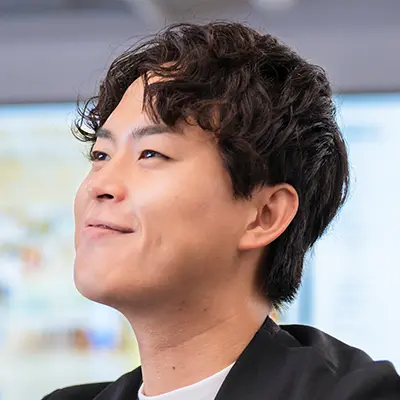 髙橋智:
私は前職で窓サッシを中心に外装の設計に携わっていました。その道のスペシャリストを目指せる恵まれた環境でしたが、30歳を目前にして、自分が本当にやりたいことは何かを考えたときに、部分を極めるよりも建築全体を知りたいと思ったことがきっかけです。類設計室のことを知ったのは、前職でお世話になっていた先輩が「本の森ちゅうおう」の外装設計を担当していたから。面白い建築をしているなと思っていました。採用担当の方との面談を重ねるうちに、ここなら難易度の高いプロジェクトに挑戦できる、技術力を磨いていける環境があるなと、前向きになれました。
髙橋智:
私は前職で窓サッシを中心に外装の設計に携わっていました。その道のスペシャリストを目指せる恵まれた環境でしたが、30歳を目前にして、自分が本当にやりたいことは何かを考えたときに、部分を極めるよりも建築全体を知りたいと思ったことがきっかけです。類設計室のことを知ったのは、前職でお世話になっていた先輩が「本の森ちゅうおう」の外装設計を担当していたから。面白い建築をしているなと思っていました。採用担当の方との面談を重ねるうちに、ここなら難易度の高いプロジェクトに挑戦できる、技術力を磨いていける環境があるなと、前向きになれました。
 桑島:
どんな建築をつくっているか、というのは私も重要視したところです。実際に類設計室のつくった建築を見に行きましたが、空間に対してとことん追求していることが感じられました。動線計画や家具の配置、照明の位置など細かいところまで設計されていて。設計のなかで使う人にとことん寄り添っている姿勢は、入る前から魅力に感じていました。
桑島:
どんな建築をつくっているか、というのは私も重要視したところです。実際に類設計室のつくった建築を見に行きましたが、空間に対してとことん追求していることが感じられました。動線計画や家具の配置、照明の位置など細かいところまで設計されていて。設計のなかで使う人にとことん寄り添っている姿勢は、入る前から魅力に感じていました。
 高橋宏:
私はちょっと特殊で、類設計室には一度新卒で設計事業部に入社していたんです。また戻ってきたのは、直属だった先輩に誘われたのがきっかけ。プライベートでも遊びに行ったりする仲で、辞めてからも半年に1回くらい連絡を取り合っていて。あるとき「戻ってこないか」と誘われました。ちょうど私も転職先での仕事からステップアップを考えていた時期だったんです。一度は辞めてしまったけど、類設計室は自分に合っている場所だったので、もう1回チャレンジできるならと戻ってきました。
高橋宏:
私はちょっと特殊で、類設計室には一度新卒で設計事業部に入社していたんです。また戻ってきたのは、直属だった先輩に誘われたのがきっかけ。プライベートでも遊びに行ったりする仲で、辞めてからも半年に1回くらい連絡を取り合っていて。あるとき「戻ってこないか」と誘われました。ちょうど私も転職先での仕事からステップアップを考えていた時期だったんです。一度は辞めてしまったけど、類設計室は自分に合っている場所だったので、もう1回チャレンジできるならと戻ってきました。
 菊地:
高橋さんは今、経営戦略課にいらっしゃいますけど、設計事業部ではない部署を選んだ理由はなんだったんですか?
菊地:
高橋さんは今、経営戦略課にいらっしゃいますけど、設計事業部ではない部署を選んだ理由はなんだったんですか?
 高橋宏:
先輩から誘われたときに経営戦略課という部署を薦められたんです。もともと新卒で入った時も、多事業展開をしているところが面白いなという理由で入りました。カムバック採用の話を受けたときに、「戻れる機会があるならどこでも戻ります」という気持ちもありましたし、何より、設計を超えて事業を考える側にチャレンジできるチャンスだと思いました。
高橋宏:
先輩から誘われたときに経営戦略課という部署を薦められたんです。もともと新卒で入った時も、多事業展開をしているところが面白いなという理由で入りました。カムバック採用の話を受けたときに、「戻れる機会があるならどこでも戻ります」という気持ちもありましたし、何より、設計を超えて事業を考える側にチャレンジできるチャンスだと思いました。


今どんな仕事を任されて、どんなことに挑戦していますか?
 高橋宏:
「こども建築塾」のカリキュラム開発から企画運営をやっていて、教育事業部と共創して、子どもたちにものづくりやデザインの楽しさを伝えています。新しい事業をつくるのは難しさもあるけれど、やっぱり面白い。あとは今、河川敷でにぎわいづくりの事業を計画していますが、インフラの整備やエリアの配置とか、建築や土木の要素もあって。これまで自分が身に付けてきたスキルとつながっている部分もある。建築設計の経験も活かしつつ、対象領域が広がったというイメージです。建物の設計を飛び越えて、事業を設計しているっていう感覚に近いです。
高橋宏:
「こども建築塾」のカリキュラム開発から企画運営をやっていて、教育事業部と共創して、子どもたちにものづくりやデザインの楽しさを伝えています。新しい事業をつくるのは難しさもあるけれど、やっぱり面白い。あとは今、河川敷でにぎわいづくりの事業を計画していますが、インフラの整備やエリアの配置とか、建築や土木の要素もあって。これまで自分が身に付けてきたスキルとつながっている部分もある。建築設計の経験も活かしつつ、対象領域が広がったというイメージです。建物の設計を飛び越えて、事業を設計しているっていう感覚に近いです。
 菊地:
設計をやる中でも高橋さんと似た感覚はあります。類設計室に来てからは、設計を通して、お客さんの事業を一緒につくっていると感じられる。私は今、都内の産業活性のための拠点整備で意匠設計を担当していますが、予定地の東京都大田区はものづくりが盛んなエリアです。ものづくり従事者の高齢化と後継者問題を解決するために、地域住民や工業界で働いている方々、日本でものづくりに挑戦したい海外の方々のために、住居やものづくり拠点、コミュニティセンターをつくっています。ただ空間をつくるだけではなく、地域の未来づくり、社会貢献にもつながる。そういった建築を飛び超えた視点で設計に向き合えることにやりがいを感じています。
菊地:
設計をやる中でも高橋さんと似た感覚はあります。類設計室に来てからは、設計を通して、お客さんの事業を一緒につくっていると感じられる。私は今、都内の産業活性のための拠点整備で意匠設計を担当していますが、予定地の東京都大田区はものづくりが盛んなエリアです。ものづくり従事者の高齢化と後継者問題を解決するために、地域住民や工業界で働いている方々、日本でものづくりに挑戦したい海外の方々のために、住居やものづくり拠点、コミュニティセンターをつくっています。ただ空間をつくるだけではなく、地域の未来づくり、社会貢献にもつながる。そういった建築を飛び超えた視点で設計に向き合えることにやりがいを感じています。
 高橋宏:
類設計室だと設計をする前に、とことんお客さんに向き合うよね。ときには、その会社についてお客さんよりも詳しくなっちゃうくらい。そのスタンスは設計事業部も経営戦略課も同じだと思います。
高橋宏:
類設計室だと設計をする前に、とことんお客さんに向き合うよね。ときには、その会社についてお客さんよりも詳しくなっちゃうくらい。そのスタンスは設計事業部も経営戦略課も同じだと思います。
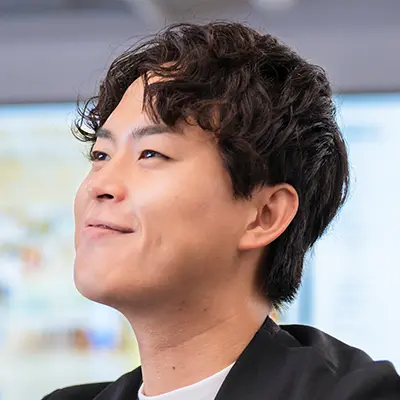 髙橋智:
私は公共施設を中心に様々なジャンルの構造設計に携わっています。最近では、菊地さんと同じ物件の構造設計に主担当として関わっています。構造設計は前職の外装設計と関わりの大きい領域でしたが、未経験に近い業務になります。けれども入社半年で物件主担当という責任のある仕事に挑戦できているのは、周りのサポートや育成環境がよく整っているおかげだと思っています。
髙橋智:
私は公共施設を中心に様々なジャンルの構造設計に携わっています。最近では、菊地さんと同じ物件の構造設計に主担当として関わっています。構造設計は前職の外装設計と関わりの大きい領域でしたが、未経験に近い業務になります。けれども入社半年で物件主担当という責任のある仕事に挑戦できているのは、周りのサポートや育成環境がよく整っているおかげだと思っています。
 桑島:
私もまだ少しずつ学んでいる段階だけど、先輩が若手をサポートして引っ張ってくれるので、経験の浅いうちからプロジェクトに自分主体でどんどん挑戦していけるよね。
桑島:
私もまだ少しずつ学んでいる段階だけど、先輩が若手をサポートして引っ張ってくれるので、経験の浅いうちからプロジェクトに自分主体でどんどん挑戦していけるよね。


前職とどんな違いがありましたか?

 桑島:
前職がアトリエ系の設計事務所だったので、それと比べると類設計室の扱っている物件の規模は大きいし、建築用途の種類も多い。私もいま用途の異なるプロジェクトに3つ関わっています。ただ、一番大きな違いは、意匠・構造・設備が一体となってプロジェクトを進めているところ。類設計室は特に、部門をまたいだ連携や設計提案づくりの機会や意識も高かったので、みんなで設計をしているという一体感がある。
桑島:
前職がアトリエ系の設計事務所だったので、それと比べると類設計室の扱っている物件の規模は大きいし、建築用途の種類も多い。私もいま用途の異なるプロジェクトに3つ関わっています。ただ、一番大きな違いは、意匠・構造・設備が一体となってプロジェクトを進めているところ。類設計室は特に、部門をまたいだ連携や設計提案づくりの機会や意識も高かったので、みんなで設計をしているという一体感がある。
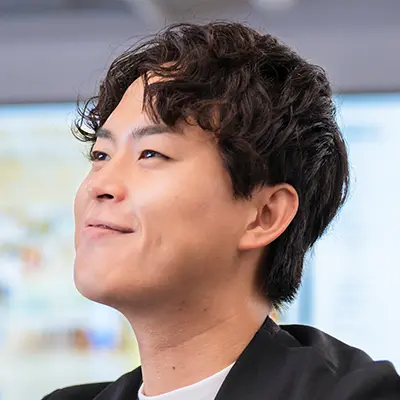 髙橋智:
設計という仕事は他分野の知識も含め幅広い思考が求められますよね。今は構造設計に携わっていますが、意匠・構造・設備との距離が近いことやお互いが対等に業務に携わっているという雰囲気があるから、自身の提案でデザインが変わることもありますし、そういった裁量の大きさも、楽しく仕事をできる要因になっていると思います。
髙橋智:
設計という仕事は他分野の知識も含め幅広い思考が求められますよね。今は構造設計に携わっていますが、意匠・構造・設備との距離が近いことやお互いが対等に業務に携わっているという雰囲気があるから、自身の提案でデザインが変わることもありますし、そういった裁量の大きさも、楽しく仕事をできる要因になっていると思います。
 高橋宏:
設計の部門間の距離が近いというのももちろんだけど、他事業部とのつながりもたくさんありますよね。
高橋宏:
設計の部門間の距離が近いというのももちろんだけど、他事業部とのつながりもたくさんありますよね。
 菊地:
私も入社して他事業部とのつながりの多さに驚きました。特に農園事業部には一週間の他事業部研修でお世話になりました。設計事業部に入ったのに農園研修をするなんて正直びっくりしましたが、設計と比べて短いサイクルの中で仕事が進む環境下で、段取り力や軌道修正方法など日頃の仕事の仕方を見直す機会にもなって充実した一週間でした。研修以外にも全事業部が参加する会議があって、コミュニケーションを取る機会が豊富です。今後の事業の可能性も広がっていて、面白みを感じています。
菊地:
私も入社して他事業部とのつながりの多さに驚きました。特に農園事業部には一週間の他事業部研修でお世話になりました。設計事業部に入ったのに農園研修をするなんて正直びっくりしましたが、設計と比べて短いサイクルの中で仕事が進む環境下で、段取り力や軌道修正方法など日頃の仕事の仕方を見直す機会にもなって充実した一週間でした。研修以外にも全事業部が参加する会議があって、コミュニケーションを取る機会が豊富です。今後の事業の可能性も広がっていて、面白みを感じています。


自身の目指すキャリアや将来像を聞かせてください
 桑島:
今まで意匠設計をやってきたので、それを基礎として、さらに経験を重ねていきたい。構造や設備など他部門との会話のなかで生まれてくるアイディアを探求し、そこから生み出されるデザインに挑戦することで、新しい建築を生み出せるようになりたいと思っています。
桑島:
今まで意匠設計をやってきたので、それを基礎として、さらに経験を重ねていきたい。構造や設備など他部門との会話のなかで生まれてくるアイディアを探求し、そこから生み出されるデザインに挑戦することで、新しい建築を生み出せるようになりたいと思っています。
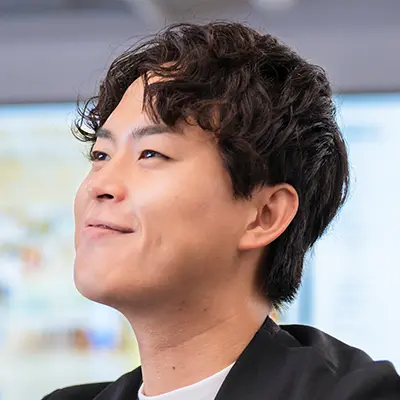 髙橋智:
私も意匠や設備といった他の部門も今後経験し、広い視野で建築を見れるようになりたいです。また類設計室のプロジェクトは建築以外の業界知識も深いところまで掘り下げて、理解して、運営していく必要がある。前職の知見も活かしながら、建築の枠に捉われない提案ができるようになりたいです。
髙橋智:
私も意匠や設備といった他の部門も今後経験し、広い視野で建築を見れるようになりたいです。また類設計室のプロジェクトは建築以外の業界知識も深いところまで掘り下げて、理解して、運営していく必要がある。前職の知見も活かしながら、建築の枠に捉われない提案ができるようになりたいです。
 菊地:
設計をする上では、建築の知識や技術だけではなくて、プロジェクトを運営するスキルも求められますよね。今はまだ教えてもらうことも多いですが、みんなに信頼されるために、チームのマネジメントや雰囲気づくりも担っていけるような存在になりたいです。
菊地:
設計をする上では、建築の知識や技術だけではなくて、プロジェクトを運営するスキルも求められますよね。今はまだ教えてもらうことも多いですが、みんなに信頼されるために、チームのマネジメントや雰囲気づくりも担っていけるような存在になりたいです。
 桑島:
一人で頭を抱えて追い詰められた状態で考えた建物よりも、みんなで闊達に意見を出し合いながらつくった建物やプロジェクトって魅力的ですよね。
桑島:
一人で頭を抱えて追い詰められた状態で考えた建物よりも、みんなで闊達に意見を出し合いながらつくった建物やプロジェクトって魅力的ですよね。
 高橋宏:
私は、「こども建築塾」をもっと広げたいと思っています。類設計室だけじゃなくて、他の設計事務所がこのプログラムをやったりできないかなって。建築業界には職人不足といった社会問題があり、こども建築塾には、そうした課題にも応えられる可能性を感じています。この事業をどんどん発展させて、社会的にも意義のあるものにしていきたいと思っています。
高橋宏:
私は、「こども建築塾」をもっと広げたいと思っています。類設計室だけじゃなくて、他の設計事務所がこのプログラムをやったりできないかなって。建築業界には職人不足といった社会問題があり、こども建築塾には、そうした課題にも応えられる可能性を感じています。この事業をどんどん発展させて、社会的にも意義のあるものにしていきたいと思っています。
 菊地:
これから外部の企業や社会とのつながりもどんどん増えていくと思うと、ワクワクしますね。
菊地:
これから外部の企業や社会とのつながりもどんどん増えていくと思うと、ワクワクしますね。

最後に、類設計室をアピールしていただけますか?

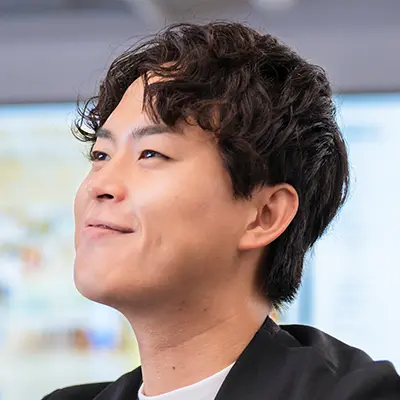 髙橋智:
類設計室はその人のワクワク感を大事にしている会社です。何か新しいことができないか、常に自分で発信して提案できる。ワクワク感や活力を持って働きたい人にはとても良い環境なのではないかと思います。
髙橋智:
類設計室はその人のワクワク感を大事にしている会社です。何か新しいことができないか、常に自分で発信して提案できる。ワクワク感や活力を持って働きたい人にはとても良い環境なのではないかと思います。
 菊地:
設計職って、一人黙々とパソコンに向かって図面を書くイメージもあると思いますが、類設計室では意匠・設備・構造とともに創る、そういった闊達な議論をする風土が根付いています。また、類設計室には設計業務以外の活動もたくさんあります。例えば、私は東京本社の改修プロジェクトとその運用考案にも携わらせていただきました。設計の案件以外でも社内と関わりながら会社づくりの一員となれることが魅力だと思います。
菊地:
設計職って、一人黙々とパソコンに向かって図面を書くイメージもあると思いますが、類設計室では意匠・設備・構造とともに創る、そういった闊達な議論をする風土が根付いています。また、類設計室には設計業務以外の活動もたくさんあります。例えば、私は東京本社の改修プロジェクトとその運用考案にも携わらせていただきました。設計の案件以外でも社内と関わりながら会社づくりの一員となれることが魅力だと思います。
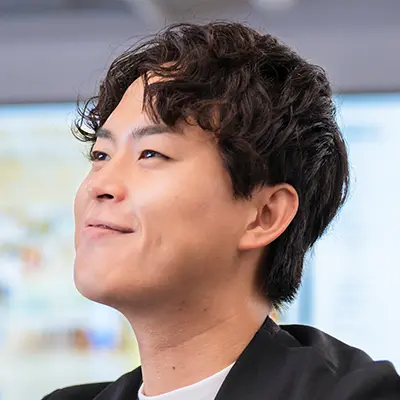 髙橋智:
いろいろなひとと仕事をするなかで、さまざまな刺激がもらえたりしますね。
髙橋智:
いろいろなひとと仕事をするなかで、さまざまな刺激がもらえたりしますね。
 菊地:
そうですね。想像力が広がるというか。そうした活動を踏まえた上で業務に戻ると、また違う視点で設計に向き合えることがあります。
菊地:
そうですね。想像力が広がるというか。そうした活動を踏まえた上で業務に戻ると、また違う視点で設計に向き合えることがあります。
 桑島:
ワクワク感もそうですが、学ぶことに対して貪欲というか、みんな積極的だから、他の人から新しい視点を学ぶことも多い。常に学び続け、進化し続ける会社だと思います。
桑島:
ワクワク感もそうですが、学ぶことに対して貪欲というか、みんな積極的だから、他の人から新しい視点を学ぶことも多い。常に学び続け、進化し続ける会社だと思います。
 高橋宏:
多事業態でいろんな挑戦をしているからこそ、社内だけじゃなく、社外との繋がりがどんどん広がっています。自分の世界や視野を広げたいと思っている方に来てもらえたらと感じます。自分たちの手で会社を創っていく・育てていく楽しさを味わっていきたいと思います。
高橋宏:
多事業態でいろんな挑戦をしているからこそ、社内だけじゃなく、社外との繋がりがどんどん広がっています。自分の世界や視野を広げたいと思っている方に来てもらえたらと感じます。自分たちの手で会社を創っていく・育てていく楽しさを味わっていきたいと思います。

※所属、仕事内容は取材当時のものです。