東京設計室
構造設計部
寺本 圭吾Keigo Teramoto
2022年入社
入社年次に捉われず成長できるチャンスがたくさんあり、早いうちから裁量権を持って仕事ができるのが類設計室の魅力のひとつ。ここでは、設計事業部の入社1年目から3年目までの新人・若手たちに、どんな成長機会があるのか、たっぷり話を聞きました。

なぜ類設計室に入社を決めたのですか?
 川端:
クライアントの未来を共に追求する設計姿勢に強く惹かれました。建築というのはアプローチであって、その先に活力ある社会の実現を目指している。その姿にすごく可能性を感じたのを覚えています。
川端:
クライアントの未来を共に追求する設計姿勢に強く惹かれました。建築というのはアプローチであって、その先に活力ある社会の実現を目指している。その姿にすごく可能性を感じたのを覚えています。
 藤間:
設計に関わりながら多事業に触れられるところも魅力でしたが、最終的な決め手になったのは、誰のどんな夢でも自分ごととして真剣に向き合ってくれる人がいる会社だと感じたからです。
藤間:
設計に関わりながら多事業に触れられるところも魅力でしたが、最終的な決め手になったのは、誰のどんな夢でも自分ごととして真剣に向き合ってくれる人がいる会社だと感じたからです。
 山田:
私もそうですね。この会社なら、思い描く提案が本当に実現できる。そう思えたのは、社員の皆さんの人に向き合う姿勢や、熱量の高さ、活力が他の会社とは違うと感じたからです。
山田:
私もそうですね。この会社なら、思い描く提案が本当に実現できる。そう思えたのは、社員の皆さんの人に向き合う姿勢や、熱量の高さ、活力が他の会社とは違うと感じたからです。
 寺本:
他の皆さんと同じで、社員一人ひとりの設計への熱量や温かさに触れてここで働きたいと考えました。決め手になったのは、2週間のインターンシップ。当時は設計士の仕事をぼんやりとしかイメージできていなかったんですが、一緒に課題を追求した先輩社員の皆さんが、私たち学生に対しても本気で向き合ってくれる魅力的な人ばかりで、ここで働きたいと思うようになりました。
寺本:
他の皆さんと同じで、社員一人ひとりの設計への熱量や温かさに触れてここで働きたいと考えました。決め手になったのは、2週間のインターンシップ。当時は設計士の仕事をぼんやりとしかイメージできていなかったんですが、一緒に課題を追求した先輩社員の皆さんが、私たち学生に対しても本気で向き合ってくれる魅力的な人ばかりで、ここで働きたいと思うようになりました。
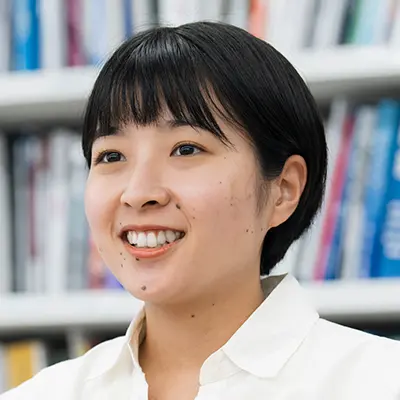 関根:
私も入社の決め手はインターンシップですね。インターンシップ自体は何社か参加したのですが、学生用のインターンシップ課題に取り組んで最後に発表して終わり、というのがほとんど。でも類設計室は、実際に物件の課題を追求する場に混ぜてもらって、最終日にはその物件の責任者であるディレクターから、「この値はどこから持ってきたの?」「これはどういうこと?」と質問攻めに合いまして(笑)。その時、ああ自分も物件を作っている一員だったんだと気付かされたんです。インターン生に過ぎないのに、ともに働く仲間として対等に接してもらえたことがすごく印象に残っています。
関根:
私も入社の決め手はインターンシップですね。インターンシップ自体は何社か参加したのですが、学生用のインターンシップ課題に取り組んで最後に発表して終わり、というのがほとんど。でも類設計室は、実際に物件の課題を追求する場に混ぜてもらって、最終日にはその物件の責任者であるディレクターから、「この値はどこから持ってきたの?」「これはどういうこと?」と質問攻めに合いまして(笑)。その時、ああ自分も物件を作っている一員だったんだと気付かされたんです。インターン生に過ぎないのに、ともに働く仲間として対等に接してもらえたことがすごく印象に残っています。


成長スピードが速いのも類設計室の特徴だと思いますが、
その実感はありますか?
 川端:
それは入社してからも強く感じる部分です。最初の1年間はほぼ研修で終わる会社もあるなかで、うちは約1ヶ月の研修を終えたら、すぐに実務課題を担当というスピード感です。私は入社1年目から現場でゼネコンさんとのやりとりを任されながら、カラースキームやサインの検討、納まりの検討を担当しました。学生の頃の設計課題と違い、実際に対象がいて、つくったものが1分の1で建つ。自分の描いていた線が実際に目の前に現れるっていうのは本当に感慨深かったです。
川端:
それは入社してからも強く感じる部分です。最初の1年間はほぼ研修で終わる会社もあるなかで、うちは約1ヶ月の研修を終えたら、すぐに実務課題を担当というスピード感です。私は入社1年目から現場でゼネコンさんとのやりとりを任されながら、カラースキームやサインの検討、納まりの検討を担当しました。学生の頃の設計課題と違い、実際に対象がいて、つくったものが1分の1で建つ。自分の描いていた線が実際に目の前に現れるっていうのは本当に感慨深かったです。
 寺本:
成長機会でいけば、僕も入社2ヶ月目の時に参加したプロポーザルで、意識が大きく変わりましたね。単なる作業スタッフではなく、いちメンバーとして、意匠・構造・設備どの分野においても分け隔てなく意見を求められることにも驚きました。それまでは構造設計者=計算する人という勝手なイメージを持っていたのですが、その手前のクライアントの想いや課題を深く理解して、その上で設計を考える。そうすることで、建物の見え方や捉え方が変わるんです。この時の経験から、構造設計に対する意識ががらっと変わりました。
寺本:
成長機会でいけば、僕も入社2ヶ月目の時に参加したプロポーザルで、意識が大きく変わりましたね。単なる作業スタッフではなく、いちメンバーとして、意匠・構造・設備どの分野においても分け隔てなく意見を求められることにも驚きました。それまでは構造設計者=計算する人という勝手なイメージを持っていたのですが、その手前のクライアントの想いや課題を深く理解して、その上で設計を考える。そうすることで、建物の見え方や捉え方が変わるんです。この時の経験から、構造設計に対する意識ががらっと変わりました。
 山田:
僕も入社1年目の時にプロポーザルに参加したのですが、企業の志や、使う人、地域への思いを徹底的に掘り下げて、それを建築の形に翻訳していくプロセスに早いうちから関わることができて、すごく刺激をもらいました。ああいった圧力の高い環境に身を置くことで、早く成長して先輩たちと同じ視点に立ちたいと思うようになりました。
山田:
僕も入社1年目の時にプロポーザルに参加したのですが、企業の志や、使う人、地域への思いを徹底的に掘り下げて、それを建築の形に翻訳していくプロセスに早いうちから関わることができて、すごく刺激をもらいました。ああいった圧力の高い環境に身を置くことで、早く成長して先輩たちと同じ視点に立ちたいと思うようになりました。
 川端:
仕事以外でも自主的にスキルを磨く機会がたくさんあります。寺本さんが主催してくれた勉強会では、1泊2日で長野に旅行にも行きました。自社作品の長野オリンピックスタジアムへ、当時の担当デザイナーと一緒に見に行ってスケッチしたんですよね。
川端:
仕事以外でも自主的にスキルを磨く機会がたくさんあります。寺本さんが主催してくれた勉強会では、1泊2日で長野に旅行にも行きました。自社作品の長野オリンピックスタジアムへ、当時の担当デザイナーと一緒に見に行ってスケッチしたんですよね。
 寺本:
社内のトップデザイナーと呼ばれるベテラン社員を巻き込みながら、見学会や勉強会をいつも企画しています。その方の視点や思考を少しでも学ぼうという主旨で始めました。若手から入社3年目くらいを対象に、これまでも自社物件をスケッチしたり、自社以外のいい建築をスケッチしたりと自主的な社外活動を続けてきました。
寺本:
社内のトップデザイナーと呼ばれるベテラン社員を巻き込みながら、見学会や勉強会をいつも企画しています。その方の視点や思考を少しでも学ぼうという主旨で始めました。若手から入社3年目くらいを対象に、これまでも自社物件をスケッチしたり、自社以外のいい建築をスケッチしたりと自主的な社外活動を続けてきました。
 藤間:
そういった社内のベテランが講師となってくれる勉強会が、いくつもあります。恒例化した企画は、ベテラン社員の名前をとって○○塾と名前がつくのも面白いですよね。自分たちで勉強する場を、自分たちの手でつくっていけるところも類設計室ならではかもしれません。
藤間:
そういった社内のベテランが講師となってくれる勉強会が、いくつもあります。恒例化した企画は、ベテラン社員の名前をとって○○塾と名前がつくのも面白いですよね。自分たちで勉強する場を、自分たちの手でつくっていけるところも類設計室ならではかもしれません。


今どんな仕事を任されて、どんなことに挑戦していますか?

 川端:
東京では事務所の改修が進んでいるのですが、この事務所改修チームは若手メインで構成されているんです。開かれた共創拠点をつくろうとしているのですが、そんな共創空間に合う家具や備品を選定するのが、私の役割。入社2年目ながら、重要な役割を任せてもらっていると感じています。
川端:
東京では事務所の改修が進んでいるのですが、この事務所改修チームは若手メインで構成されているんです。開かれた共創拠点をつくろうとしているのですが、そんな共創空間に合う家具や備品を選定するのが、私の役割。入社2年目ながら、重要な役割を任せてもらっていると感じています。
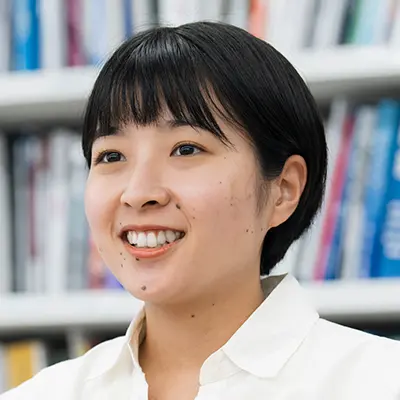 関根:
私もその改修チームのメンバーで、植栽計画をメインで任されています。業者さんとのやりとりなど社外の方と接する局面でも、「え?いいの?」というくらい、どんどん仕事を任せてもらっていますね。
関根:
私もその改修チームのメンバーで、植栽計画をメインで任されています。業者さんとのやりとりなど社外の方と接する局面でも、「え?いいの?」というくらい、どんどん仕事を任せてもらっていますね。
 藤間:
私は建物ができる上流の企画段階に携わっているのですが、お客様の期待に近いイメージ画像をAIで提案できないかリサーチしていたところ、AI追求チームが立ち上がり、現在そのメンバーになっています。入社1年目でも声を上げれば、業務を変えていくような社内の変革にも携わることができる。それも類設計室ならではだと思っています。
藤間:
私は建物ができる上流の企画段階に携わっているのですが、お客様の期待に近いイメージ画像をAIで提案できないかリサーチしていたところ、AI追求チームが立ち上がり、現在そのメンバーになっています。入社1年目でも声を上げれば、業務を変えていくような社内の変革にも携わることができる。それも類設計室ならではだと思っています。
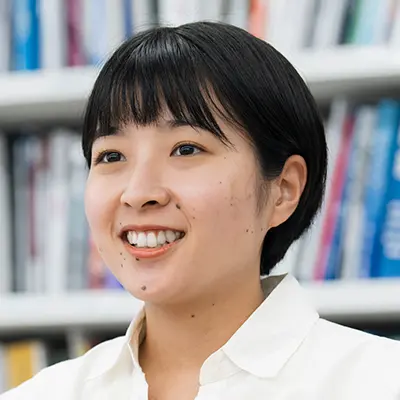 関根:
若手であっても「こんなことをやりたい!」という発信がしやすい社風ですよね。
関根:
若手であっても「こんなことをやりたい!」という発信がしやすい社風ですよね。
 藤間:
全社員が集まる全体会議でも、会議室の中央部分に新人の席がありますよね。発信を期待される社員から一番近い「スーパー内野」と呼ばれています(笑)。1年目は会議のメモを取るので精一杯という会社も多いと思いますが、類設計室では1年目にも会議の中心となるような積極的な発言を求めている。そういう周囲からの期待は常に感じます。
藤間:
全社員が集まる全体会議でも、会議室の中央部分に新人の席がありますよね。発信を期待される社員から一番近い「スーパー内野」と呼ばれています(笑)。1年目は会議のメモを取るので精一杯という会社も多いと思いますが、類設計室では1年目にも会議の中心となるような積極的な発言を求めている。そういう周囲からの期待は常に感じます。


他事業部と共創しながら、挑戦したいことはありますか?
 山田:
建てて終わりではなくて、建てた後、竣工後の運営のところにも携わってみたいと思っています。類設計室には教育事業部もあれば農園事業部もあるので、挑戦できることの幅も広いと思いますね。
山田:
建てて終わりではなくて、建てた後、竣工後の運営のところにも携わってみたいと思っています。類設計室には教育事業部もあれば農園事業部もあるので、挑戦できることの幅も広いと思いますね。
 寺本:
教育事業部と設計事業部で行っている「こども建築塾」にスタッフとして参加させてもらう機会があるのですが、子どもたちと触れ合うなかで、たくさん気づきがあって。他事業部の知見を存分に活かしながら、類設計室として新しい学校のかたちを追求していきたいと思っています。
寺本:
教育事業部と設計事業部で行っている「こども建築塾」にスタッフとして参加させてもらう機会があるのですが、子どもたちと触れ合うなかで、たくさん気づきがあって。他事業部の知見を存分に活かしながら、類設計室として新しい学校のかたちを追求していきたいと思っています。
 川端:
いま東京で設計を担当している大阪の物件があるのですが、その物件があるエリアが、ちょうど宅配事業部でポスティングを行っているエリア。小規模の小売店なのですが、そのお店の宣伝を宅配事業部と一緒にできないか、なんていう動きもあります。あとはそのお店に類農園のお野菜も置いていただくことになっていたりして。建てた後の運用のところにも、類設計室全体で関わっていける。それはすごく嬉しいことだと思いますね。
川端:
いま東京で設計を担当している大阪の物件があるのですが、その物件があるエリアが、ちょうど宅配事業部でポスティングを行っているエリア。小規模の小売店なのですが、そのお店の宣伝を宅配事業部と一緒にできないか、なんていう動きもあります。あとはそのお店に類農園のお野菜も置いていただくことになっていたりして。建てた後の運用のところにも、類設計室全体で関わっていける。それはすごく嬉しいことだと思いますね。
 藤間:
宅配事業部との共創でいうと、何か新しく建築を建てようと計画するときに、現地を知っているというのも私たちの強みだと思うんです。実際にポスティングをしてくれている配布員の方々は、そのエリアのことをよく知っている地域住民の皆さん。さらに、宅配事業部ではその地域に住む人の年齢層や家族構成などの、エリアマーケティングも行っている。企画の段階で宅配事業部の知見をお借りすることで、もっと企画の精度を高められると思っています。
藤間:
宅配事業部との共創でいうと、何か新しく建築を建てようと計画するときに、現地を知っているというのも私たちの強みだと思うんです。実際にポスティングをしてくれている配布員の方々は、そのエリアのことをよく知っている地域住民の皆さん。さらに、宅配事業部ではその地域に住む人の年齢層や家族構成などの、エリアマーケティングも行っている。企画の段階で宅配事業部の知見をお借りすることで、もっと企画の精度を高められると思っています。

最後に、類設計室とはどんな会社かアピールしていただけますか?

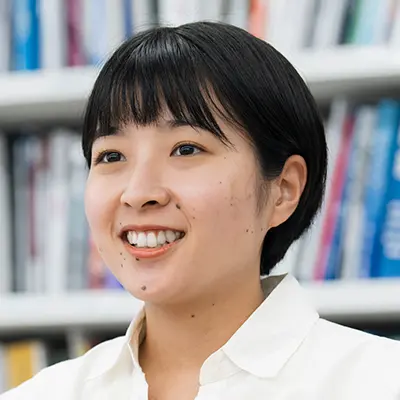 関根:
一緒に見つけてくれる、一緒につくってくれる会社だと思います。就職活動の時って、こういう建築家になりたいとか、こういう建物をつくりたいといったイメージが明確でないとダメなんじゃないかと不安になることもあると思います。私自身もそういうところがあったので。でも類設計室と出会って、「こうなりたい」とか「これがしたい」は、後から鮮明になったり、その数が増えても良いんだよなと思うようになりました。ベテランとか若手とか関係なく、誰でも新しいことに挑戦できるし、その挑戦を応援してくれる人ばかり集まっています。だから、類設計室なら自分のやりたいことを見つけられるし、実現もできると思います。
関根:
一緒に見つけてくれる、一緒につくってくれる会社だと思います。就職活動の時って、こういう建築家になりたいとか、こういう建物をつくりたいといったイメージが明確でないとダメなんじゃないかと不安になることもあると思います。私自身もそういうところがあったので。でも類設計室と出会って、「こうなりたい」とか「これがしたい」は、後から鮮明になったり、その数が増えても良いんだよなと思うようになりました。ベテランとか若手とか関係なく、誰でも新しいことに挑戦できるし、その挑戦を応援してくれる人ばかり集まっています。だから、類設計室なら自分のやりたいことを見つけられるし、実現もできると思います。
 寺本:
建築を設計するというより、社会を設計するのが類設計室。人とか地域とか社会とか、建築のその先を考えた上で、ようやく設計ができるという感覚が、類設計室に入社してからより強くなりました。建築をやりたくて入社したけれど、建築以外のことにもどんどん関心が広がっています。多事業部経営だからこそ建築以外にも対象が広がり、それが建築設計に活かされる。自分の視野を広げてくれる会社だと思います。
寺本:
建築を設計するというより、社会を設計するのが類設計室。人とか地域とか社会とか、建築のその先を考えた上で、ようやく設計ができるという感覚が、類設計室に入社してからより強くなりました。建築をやりたくて入社したけれど、建築以外のことにもどんどん関心が広がっています。多事業部経営だからこそ建築以外にも対象が広がり、それが建築設計に活かされる。自分の視野を広げてくれる会社だと思います。
 藤間:
社会を相手にしているから、いろんな考えを受け入れる土壌があるのだと思います。一言でいうなら正解・不正解をつくらない会社。間違いを恐れて発言をためらってしまうこともあると思います。ですが、新しい切り口や可能性に対して、受け入れるベースが整っているからこそ、自分の想いを素直に発信しやすい環境がここにはあります。
藤間:
社会を相手にしているから、いろんな考えを受け入れる土壌があるのだと思います。一言でいうなら正解・不正解をつくらない会社。間違いを恐れて発言をためらってしまうこともあると思います。ですが、新しい切り口や可能性に対して、受け入れるベースが整っているからこそ、自分の想いを素直に発信しやすい環境がここにはあります。
 山田:
設計という仕事自体、正解がないしね。だからこそ、自分の中に信念がないとできない仕事だと思うんです。自分が信じているものが正しいのか、強度があるものなのか、常に問い続けないといけない。建築だけではなく、社会全体を広く知ることも必要になるし、自分の考えの根拠を深く掘り下げることも必要になる。類設計室は、一人ひとりが広く深く追求し続けている会社だと思います。私もそうでしたが、自分が今まで持ってきた信念を問い直す機会が、類設計室に入社したら何度も訪れると思う。その繰り返しで、自分の信念をより強いものにしていけるんだと思います。
山田:
設計という仕事自体、正解がないしね。だからこそ、自分の中に信念がないとできない仕事だと思うんです。自分が信じているものが正しいのか、強度があるものなのか、常に問い続けないといけない。建築だけではなく、社会全体を広く知ることも必要になるし、自分の考えの根拠を深く掘り下げることも必要になる。類設計室は、一人ひとりが広く深く追求し続けている会社だと思います。私もそうでしたが、自分が今まで持ってきた信念を問い直す機会が、類設計室に入社したら何度も訪れると思う。その繰り返しで、自分の信念をより強いものにしていけるんだと思います。
 川端:
広く深く、とことん追求する会社ですよね。社会の期待をしっかり掴んで、それを超えるようなものを、それぞれの事業部が、それぞれに追求している。だから自然と対象が広く、深くなっていくのだと思います。自分の対象を広げて、どこまでも成長していける。そんな環境がここにはありますね。
川端:
広く深く、とことん追求する会社ですよね。社会の期待をしっかり掴んで、それを超えるようなものを、それぞれの事業部が、それぞれに追求している。だから自然と対象が広く、深くなっていくのだと思います。自分の対象を広げて、どこまでも成長していける。そんな環境がここにはありますね。

※所属、仕事内容は取材当時のものです。