キャリア設計図

キャリア設計図
(建築設計職編)
それぞれの適性に応じて、成長の道筋がいくつもあるのが類設計室の魅力です。広い視野、高い視座を獲得しながら、知識・技術の専門性を高める設計者もいれば、クライアントを取り巻く背景や経営戦略にまで精通する設計者もいます。
多様な経験を生かし、
チームをまとめるディレクターへ
_CAREER MODEL 入社15年目 / 小熊 耕平の場合
入社後の13年間で意匠・構造・監理・計画・企画をジョブローテーション。様々な部署での経験を生かして、現在はディレクターとしてプロジェクトチームを統括する役割を担いながら、設計室全体の人材活性化も牽引している。

主な業務経歴
- 2011年
- 設計事業部 大阪設計室の意匠設計部に配属。
- 2016年
- 同監理部に配転。『アシックス福井工場』の監理を担当。
- 2020年
- 同企画部に配転。富田まちづくり構想では、プロポーザルで企画・構想業務にまちづくり業務担当として携わる。
- 2021年
- 意匠設計の課長として、同意匠設計部に配転。
- 2024年
- 社内外の活力を高めるチーム運営が評価され、同ディレクターに抜擢。
『滋賀県東北部工業技術センター』や、『地域に根差した幼保連携型認定こども園』など多用途に渡る案件を統括。
設計力を武器に、
職種を越えていく
_CAREER MODEL 入社12年目 / 望月 宏洋の場合
設備設計からキャリアをスタート。入社6年目で設備設計部の主任を務めたのちに、高い対人スキルが評価され、2020年に営業に転向。現在は営業としてプロジェクトのマネジメント・プロデュースに携わりながら、培ったキャリアを生かして環境領域の社内外ネットワークづくり・環境設備提案の高度化を推進。

主な業務経歴
- 2014年
- 設計事業部 東京設計室の設備設計部に配属。
『江戸川区立第三松江小』の設備設計と設備監理を担当。 - 2016年
- 『荒川区立尾久図書館』などの公共施設から『フジキカイ THE BASE NAGOYA』などの民間企業オフィスを担当。
- 2019年
- 『MIC株式会社 本社』、『荒川区立尾久図書館』などの監理を担当。
- 2020年
- 東京設計室の営業部に配転。『株式会社キミカ本館』などのプロジェクトのマネジメント・プロデュースを担う。
- 2024年
- 営業課長として『旧羽田旭小学校敷地活用事業』などのプロジェクトマネジメントを担いながら、環境設備提案の高度化や設備人材の育成も推進。
視野を広げて、
心躍るデザインを生み出す
_CAREER MODEL 入社9年目 / 出田 麻子の場合
入社後、意匠・計画設計での設計経験を積み、プロジェクトの初期段階から監理段階にわたる、全体的な設計の視野を体得。今では計画設計を担いながら、中堅人材として社内の人材育成や採用活動などにも力を入れる。

主な業務経歴
人材育成ロードマップ
建築設計では意匠・構造・設備や、より上流の企画・計画など、建物に関わる総体的な統合力が必要不可欠です。類設計室では、統合力を養うための育成システムを採用しています。

入社7年目以降
設計者に求められる総合的な技術力、提案力を身につけていく。
設計者に求められる総合的な
技術力、提案力を身につけていく。
7年目以降は、建築に関する総合的な力を獲得するローテーション配置で経験を積む、一つの領域を極めるなど、人材にあった育成を行なっていきます。ローテーション配置で全く違う視点で建物を捉え直す経験は、個々の視野を広くし、視座を高めることにつながっていきます。
たとえば意匠から構造へ異動し、建物の躯体に関する知識を身に付けたのちに意匠に戻ることで、構造を把握した上で本質的な提案ができる。意匠から企画へ異動し、経営側にも関わっていくことで、事業の上位概念から建物を捉えられるようになっていく。これはあくまで一例ですが、幅広い分野の知見を蓄えることは個人の統合力を高め、キャリアをより豊かなものにしてくれるはずです。
能力開発プログラム
勉強会が活発に行われ、様々な学びの機会が日常的にあるのが類設計室。 経営課題や事業戦略も全社で共有するため、若いうちから経営視点を養い、 設計者として総合的な力を育むことができます。
「設計力」を身につける
技術追求会
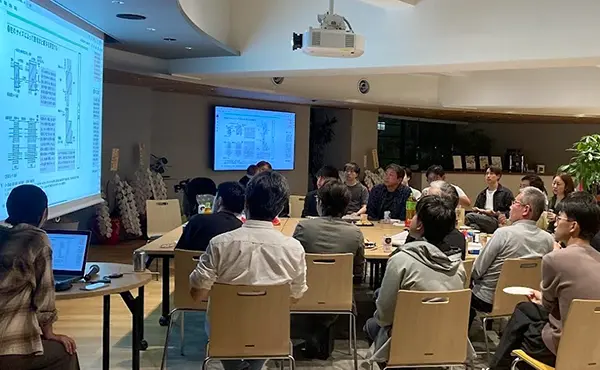
若手から働きかけて始まった勉強会のひとつ。各部門のトップアーキテクトを講師に、2週間に1度開催。具体的な物件の施工事例をもとに、あるべき設計を追求していきます。
設計レビュー

設計の各フェーズにおけるレビューは、一方的に評価される場ではなく対話型。チーム外のメンバーも交えてディスカッションをすることで、設計の高度化、人材育成にもつながっています。
共同研究

新しい建築設計を求めて、東京大学、滋賀県立大学、信州大学、九州大学など多くの大学やその研究室と、共同で研究に取り組んでいます。
「提案力」を身につける
経営会議

毎月開催する経営会議には新人や若手も参加。各事業部の経営課題や事業戦略、全社の売上もすべて共有し、経営視点を養います。
勉強会(サロン研修)

お客様により良い提案をするために社会状況や時代の潮流を正しく把握するのがサロン研修の目的。部門を横断し、様々な年代で幅広いテーマに取り組み、視野を広げます。
資格取得支援
一級勉強会

一級建築士の資格を取得するためにチームで取り組む勉強会。過去の合格者がチューターとして参加。社内勉強会に加え、勉強方法立案や模試分析など手厚いサポートにより、多くが合格を果たしています。
キャリア形成支援
1on1ミーティング
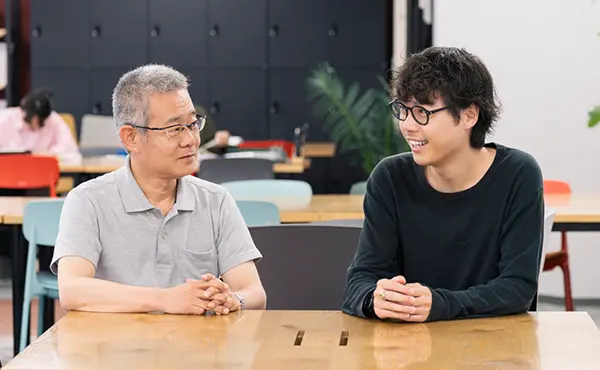
「ありたい姿」を実現していくために、上長と1on1のミーティングを定期的に実施するほか、目標設定とその振り返りを半期ごとに行い長期的なキャリア形成を支援します。







